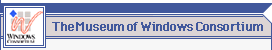Windowsの歴史を紐解く過去の記事 【1990年1月】

|
田中亘 |

|

■古川社長インタビュー ロングバージョン
1990年の年頭に雑誌の仕事でマイクロソフトの古川社長(当時)にインタビューした。当時はまだ、日本でのWindows 3.0の登場が見えていない頃で、MS-DOSが圧倒的に有利な時代だった。しかし、すでにその頃から古川社長は5年先の日本市場を頭に描いていたのかもしれない。
田中亘 アメリカではWindowsがかなり普及しています。日本はどうか。日本電気の高山氏によると,Windowsは去年のPC-9800の出荷実績370万台のうちの10パーセント。まだ日本ではWindowsの市場は小さい。それでも日本電気は,Windowsマーケットが今後じわりと広がっていくという見方をしているようです。
また、アメリカと日本のWindows市場の大きな違いはLANにあるという見方もあります。アメリカでは,LANがベースにあって,そこにWindow3.0がきたから,LANのサーバやクライアントマシーンでWindowsも使えるようになったという。ところが,日本ではLANはWindowsと同じように今後普及していくものなので、合わせて普及するのは難しいのではないか、という意見です。
古川社長はWindowsは今後日本にどう浸透していくとお考えですか。
古川社長 アメリカでWindowsが200万本とすれば,年間にアメリカで売れるマシンに対するWindowsの普及率と同じ比率が日本にも適用されるかというと,それは楽観的に見てはいけないだろうな,と思っています。その理由というのは,大きな要素があるのではないでしょうか。
その1つは,Windowsが出たときのアメリカと日本の一番大きな違いで,システムソフトウェアであるところのOSであるWindowsというものが,アメリカで小売りの商品として取り扱われたということです。これはWindows3.0が離陸したあとの日米の違う部分です。Windowsが小売りの商品であるということが何を意味するかというと,エンドユーザーさんの立場からすると,インパクトが違うんです。エッグヘッドのような小売り店が取り扱う商品であるのか,それともコンパックのようなベンダーのマシンを買うと一緒に付いてくるOSなのか,という違いは大きいです。
Windowsがどれだけ浸透していくかというのは,ぼくが良く使う表現で,システムソフトウェアというのは日本の場合は農耕民族的な広がりを示さないと根付かないと思う。対するアプリケーションというのは狩猟民族的な1-2-3とかExcelとどっちが勝つかというようなビジネスだと思う。
ところが,アメリカの場合にはシステムソフトウェアの販売そのものがまず狩猟民族的な流通を通じて「今週のヒットチャートはなに」というようなところにのっかったという意味で,爆発的に伸びた。
ところが,日本の場合,ハードウェアが各社違うから,Windows3.0をしっかりさせていかなければというメーカーの向上心の元に離陸します。ソフトバンクにしろソフトウェアジャパンにしても,今月の売れ筋のナンバー1は,Windows3.0です,という売り方をしない限り,販売のトレンドというのは,アメリカと違った様相を示すだろうと思います。
2番目の大きな違いは,システムソフトウェアの販売が,日本の場合には,まずハードウェアを売ることが前面に出てしまうことでしょう。Windows3.0を売りたいお客様は誰かというと,86ベースのV30のマシンを持っている人。そういう人に386マシンに買い替えてください,386を買えばWindows3.0動きますよ,という戦術をとる。基本的なインセンティブというのは386マシンを売るために,Windowsをプッシュしたいわけです。確かに既にPCを持っているお客様はハードディスクを買えば,フロッピーディスクを買えばWindowが動くんだけれど,そういう人たちがメインに使って欲しいのは,メーカーがシステムソフトウェアを販売する限り,どうせ買うならOS/2もWindows3.0も動く386マシンに買い替えましょうと。
アメリカの場合には,システムソフトウェアの販売は完全に,その日マシンを購入する人を対象にしたビジネスではなくて,インストールベースで,過去の4000万台あるマシンのうちの何パーセントが386で,286で,既にハードディスクもEMSメモリーもあって,そのお客様がソフトウェアを追加商品として買うところで,バッと売る。この2点が大きな違いでしょう。
確かに,Windowsを日本でも広げたいと思っているけれども,トレンドとして,いきなりアメリカの200万本で,日本の人口はアメリカの2分の1だから100万本売れるかというと,それほどオプティミスティックに考えていません。
米国で200万本売れるまでのセールス期間で,国内で20万本売ったら大成功かもしれないというようなアプローチをしなければいけない。流通のチャネル,今日PCを買う人のWindows環境を提案するか,それとも過去のPCのお客様に対してWindowsを売るかという,違いがありますから。
 |

古川社長が米国から輸入して組み立てたIMSAI8080

|
田中亘 LANの日米の差はどうですか。
古川社長 イエスです。しかし,いろいろな違いがあるにしても,Windowsは流行るだろうと思います。そして,ユーザーのWindowsの使用レベルは4段階に分けられると思います。
田中亘 その4段階とは
古川社長 まず第1段階はシェルの変わりの,もしくはメニューの変わりの,アプリケーションスウィッチャー的な感覚で,旧来のアプリケーションを使う。そういうことに十分Windowsは採用されてきた経緯があります。
Windowsを200万人が買った。果たして何に使っているのだろうと考えると,全員がExcel使ってます,PageMAKER使ってます,あれ,ちょっと数字がおかしいなって思うでしょ。200万人というのはWindowsだけを使っている人なんです。だけどWindowsについているおまけというのは,果たして実用的なものかどうかというと,あれ,と思うでしょ。やっぱり,マシンを立ちあげたときに,仕事にとりかかる前にWindowsが立ち上がって電気が付いているときにころがしておくメニューであったりシェルであるということの変わりに使われている。シェルだけだったらちょっと悲しいかなって思いますが,おまけの,例えばアイコンベースで既存のアプリケーションを動かすアプリケーションスウィッチャー的な考え方になんです。Macintoshの世界でマルチファインダが出る前にスウィッチャがありましたね。あれと同じ感覚で,例えば"松(ワープロソフト)"を動かして,ちょっと指を鳴らすようにウィンドウが小さくなって,住所録でも使って電話でもかけて,その後また"松"に戻ってくるというようなことをする。アプリケーションをアイコンベースで,DOSのコマンドをGUIで取り扱えるという部分をWindowsが担っている。それからオブジェクト指向として"松"のデータファイルでも,そのデータファイルをクリックすると"松"を引っ張ってきて自動的に立ち上がるわけでしょ。そういうことが仕事の心地よさになるってことがきっとある。
2番目と言うのは,Windowsのアプリケーションを組み合わせて使うこと。これが,Windows3.0の普及期だと思います。これは何かというと1本のアプリケーション,例えば"一太郎(ワープロソフト)"を使っていて,リセットスイッチを押して,"1-2-3(表計算ソフト)"を使うというやり方ではなくて,Windowsベースだったら,ExcelもPageMakerもWord for Windowsも指を鳴らすように切り替えて使うことによって,自分の意識を切り替えて複数のアプリケーションを使うということは,自分の仕事で使うすべての道具を机の上に広げて,組み合わせによるチョイスで自分の仕事の最適環境を作れる。組み合わせが便利でその普及もかなり長いだろうし,そこでとどまっちゃう人もいるだろうけれど。
第3番段階は,組み合わせればそれが1つのアプリケーション運用環境なんだというところが高まりを見せる。具体的にロイターの金融端末を見ると,ディーラーが売り買いをやっているときに,前の端末ではExcelがアドインソフトみたいに組み込まれている。それはディーリングルームで運用される世界時計であり,値動きであり,シミュレーションをする時にグラフを出したりする。それを実際に動かしている人たちにとってみれば,Excelとディーリングルームのソフトウェアを使っていても,Excelとワープロソフトを使っていても,その一塊がアプリケーションも切れ目など知らない世界で,完全に包括した形で1つの窓の内側の中でその1日の仕事の必須環境が揃った形で運用されてくる。
第4段階はどこへ進むかというとまさしく1つの窓の中でこの仕事とこの仕事が組合わさってやっているが,あくまで個人の仕事で,レイアウトと原稿と写真を取る人とデザインをやる人を考えてみると各々の環境の中で自分のキャリアの中で適した仕事をやって,それを統括的にレイアウトする人が別にいてということを考えると,ディーリングルームみたいに窓の内側に閉ざされた環境を全員が同じく使っているというのではなくて,ネットワークの中でその窓を通じて自分の仕事をやってそれで組み上げられた各々の仕事の結果が誰かが統括管理したり編集したりという状況になったら,おのおの窓の内側でネットワークを通じてデータを集計したりすることが,Windowsを通じて発展したときには窓の内側にあった複数の組み合わせというのがネットワークを通じて他の世界までつながるという状態に最終的にはなっていく。この4段階のステップを踏んでいくだろうと思う。
田中亘 そのステップは1から順に進んで行くのか。
古川社長 果たしてアメリカでこの4段階までいっている下地があるのかと思う。第1段階と第2段階の間を行き来している人もいれば,ロイターのように最初から3段階を仕掛けられていながら,それがWindowsであることにも気づかないケースもある。日本でも経済ジャーナルというテレビ番組がありますが,2人のキャスターの間に端末がボーンと置いてあって,その端末の前にロイターという札が立っている。テレビに出ている人も,テレビを見ている人も,WindowsやExcelが走っていることを全く知らないと思う。
田中亘 Windowsを使っていることに気がつかない。全く意識する必要がない。
古川社長 日本航空のアクセスという予約端末システムがある。あれは,Windowsなんだけど,旅行代理店の方が予約を入れながら,「Windowsにもう1本アプリケーションを乗せたい」とかは思っていない。
4段階のステップはシーケンシャルに来るのではなくて,オーバーラップしながら訪れると思う。WindowsというとMacintosh的な環境できれいにGUIが出るとかと,耳にタコができるほど言われているが,それよりもこの4段階を認識してもらった方がいいと思う。
例えば,シェルとしての使い方はこの範囲で,それでも使う価値があるんです。組み合わせて使ったらこうですよ。そのためにはアプリケーションがたくさんなければいけない。アプリケーションの数がなくても統合的な環境,ロイターのようなアプローチ,日本航空のようなアプローチ,Windowsそのものがオフィスにとっていかに心地よいかがわかる。ディーリングルームで1人1台づつ使うならそれはそれでいい。ネットワークを通じて使う中では,別の次元のことができる。Windowsの中で,マイクロソフトでなく,誰かが商売をするなら,この4つの段階をお客様に提供できたらWindowsのインテグレータとしてなり,PCメーカーとしてなり成功する。
田中亘 MAC EXPOでDOS対MACというテーマの対談に出られると
古川社長 戸島さんと林さんが出ると聞き,MacがWindowsとの対決という局面で対決するなら私は出ないといいました。
田中亘 日本航空の場合,予約システムとしてはなぜ,Windowsを採用したのでしょうか。
古川社長 予約端末と言うのはお客さんに背中を向けていた。これから先,お客様と一緒にプランを練りながら,確認して予約するシステムというのが,付加価値をどう付けるかということが商売に係わっている旅行業界にとって必要なんです。安い航空券を売るというのは何の付加価値もないけれども,定価で航空券を買ってもらうには,自動的にネームタッグに名前を入れたり,スケジュールをきれいに書き上げたりといったシステムをつくることも必要。Windowsでこうした付加価値を最短の工数で実行可能です。端末をお客様に向ければ,座席の具体的なイメージを見せることもできるでしょう。こうした動きはIATAのなかでも,ルフトハンザ,アメリカンエアと,ユナイテッド,ブリティッシュエア,アリタリアにもある。
お客様に対するプレゼンテーション効果だけでなく,旅行会社にとってのコスト削減にもWindowsは貢献できます。予約システムの端末からコマンドを入れるには熟練が必要です。全国の旅行代理店の予約担当者が予約・解約などのために多くのコードを間違えなく入力できるようになるまでには大変な工数がかかるのです。こうした情報をホストマシンに入れようとしたら,全世界のシステムを変えなければならない。そこで,視覚的に簡単にして,こうした知識ベースをローカルにアップデートできて,サーバまでロードしておけば,そのサーバレベルで,いきなり予約をとらないで,サーバ側でチェックできるような機構を置いて,端末に仕掛けるとか,1台しか端末がないなら,端末側にインテリジェンスをもってきて,複雑なキーシークエンスではなくて,完全なメニュー形式でメニューを選べる。ダム端末でエントリーする限り,インテリジェンスをローカルに持たせるというのを実現できるのが,Windows端末のメリット。ホストも全とっかえ,端末も全とっかえというのは,莫大な費用がかかる。320端末もまだここにあるんだけれども,実はもう1台入ってきた端末は遊んでいて,インテリジェンスを持っているとしたら,自然に切り替えが進められます。全体の20パーセントだけまず切り替えて,次50パーセント切り替えるといったパスを作って行く。
田中亘 いちばん顕著なGUIの事例ですけど,今のパソコンとパソコン上のWindows上のスタンドアロンのアプリケーションとでは注目されていない。
古川社長 Windows上でExcelやPageMekerが動かしたいといった企業がなぜWindowsを採用するのか。イメージがわかなかったのですが,それは,インテリジェンスは人へ教育すればいいのか,コンピュータが柔らかく教えればいいのか,の回答になります。アプリケーションを1つ2つ教えるには教育のプロセスをどうしたらよいか。マニュアルを熱心に読んで一生懸命使い方を覚える人ばかりではない。そうでない人もコンピュータをいじるようになる。いやいやながらコンピュータを使う人たちの教育をどうするか。1つのソフトの使い方を覚えれば他のソフトも使える方が教育のコストや低く済む。1-2-3も一太郎もWindowsの中で同じ環境で使えるというのはいいことでしょう。
田中亘 日本電気の場合,Windowsは98全体の10パーセント。Windowsに対する期待はEAの価格設定44万8000円に現れている。386のDA機を普及機として狙っている。386を売っていく要素であるWindows3.0に対する期待であり,逆に386マシンによってWindows3.0が普及して欲しいということだろう。
同様に他のメーカーもWindows3.0でビジネスチャンスが出てくるのだろうか。
古川社長 EA構想ってやつですね。ハードウェアではマイクロメインフレーム結合はもう古い。ホスト側のデータベースとローカルのExcelというインタフェースをソフトベースで結び付けることが新しいマイクロメインフレームなんだということですね。これはいいセンスだとおもった。ExcelはExcelとして,あるいはWindowsを単体として,ネットワークという時代だという前に,いっちゃわるいけどACOSがSISという構想の中で98を端末に使いましょうという発想は出てこない。富士通はKシリーズを持ってきて,NECはESWの4800だとかACOSでSISを標榜している。98は98のカルチャがあり,5200は5200のカルチャがある。基本的に境界線を作ることが無意味なんです。クライアント・サーバコンピューティングやるなら,3090とアS400があってPS/55があると。PS/55のサーバがあってクライアントがあるという発想のなかで,ちょっとびっくりするところがある。今のオフコンの存在を認めながら,PCはPCの役目をはたしていく。そういうことにつながる。Windowsによって今まで孤立していたPCをもっとつなげられる可能性が出てくる。
田中亘 ペンWindowsについて
古川社長 誤解して欲しくないのは,文字認識の部分とユーザーインタフェースの部分を分けて考えなければいけないんです。文字認識に関して,マイクロソフトはWindowsでやるといっても,文字認識のところでIBM,富士通,NECなどが研究所でやっているものとケンカしても始まらない。コモンユーザーアクセスに関しては独自のインタフェースが欲しくていちいちドロップダウンメニューとかでやるのは面倒くさいでしょ。いいなと思うのはインタフェースさえ定めるとExcelでも1-2-3でも動くという状態になっていて,既存のアプリはもう1回マウスを使ったオペレーションの場合,ペンで動かしたときにこういうインタフェースを確立したら,ペンでも使いものになるなと思う。ラインマーカーで線を引っ張るというのがあるけれども,3Page分引くのはたいへん。マウスで縦方向にドラッグするのはいいけれど,ペンで縦方向に動かすのは気持ち悪いでしょう。それは人間のインタフェースと違うからなんです。だから,ペンの場合,範囲指定の初めと終わりにに丸書いてちょんです。アプリケーション側はどんな苦労してインタフェースを変えたかというと,アプリケーションは全然いじっていないというんです。Windowsもマウスをキーとして使っている。キーとして使うインタフェースの代わりに,ペンで入力したアクションを解析してWindows側に渡している。コマンドと同じものに翻訳して渡している。ペンで入力するような小型コンピュータは確実に現れるでしょう。そのときのわれわれのスタンディングポジションは既存のWindowsアプリケーションが何の変更もなしに動くということをさわやかにきっと認めていただけるということに自信があります。新しいインタフェースが提供されているので,これにあった新しいアプリケーションも提供したい。そのための仕掛けもたくさんちりばめています。
(著者:田中亘 wataru@yunto.co.jp)
|