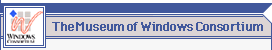Windows 3.1は、1993年に登場してから一年ですっかり日本のパソコン市場に定着した。新規に出荷されるパソコンの多くが、Windows を最初から使える状態にした製品構成になっている。現在のパソコン市場において、「パソコンを使う」という言葉そのものが、もはや「Windows の利用」を明確に意図したものになった。
★激動の90年代を乗り切るキーワードがWindows
21世紀を目前にひかえたこれからの企業活動にとって、パソコンを活用した情報ネットワークや経営環境の構築は、避けて通ることのできない課題となっている。その昔、読み書き算盤が商いにとっての必須能力といわれた時代から、現在は語学力と表現能力にパソコン活用という三大能力が、組織の中で活躍する個人に要求されている。
中でも、新しい時代に向けた経営や管理能力の育成にとって、パソコンは欠かすことのできない道具となっている。表計算ソフトによる数字の集計から、データベースソフトを活用した情報収集や、ワープロソフトによる迅速な報告書作成など、ビジネスに関係するあらゆるシーンで、パソコンとアプリケーションの組み合わせによるバックアップが、効率よく仕事をこなす企業環境を作り上げてきた。
そして、世界的な不況が叫ばれる中にあって、確実に業績を上げ、競争力を回復している企業のほとんどが、パソコンを最大限に活用した情報ネットワークと経営戦略によって、21世紀に向けた組織作りを実現している。
そんな欧米におけるパソコン活用は、すなわちWindows の利用そのものを意味するようになっている。Windows であれば、いままでパソコンの利用に戸惑っていた人たちも、自分に必要な情報や数値を簡単な操作で取り出せるようになる。このような「あらゆる情報をいつでも手元に」参照できる環境が、企業の中に構築されることによって、社員の意志の疎通が円滑になり、同時に無駄な会議の時間や意志決定を送らせるような情報の遅延がなくなる。
情報疎通の円滑さの実現は、その次のステップとして、企業内での積極的な行動や活動の原動力となる。新しい市場への挑戦や、いままでの仕組みに対する全面的な見直しや改革を推進する力となり、それが結果として企業の再生や、より一層の発展を喚起する。
そんな理想的な企業の成長にとって、Windows とパソコンが、とても重要な役割を示すようになってきたのである。
★ネットワークを実現するWindows NT
激動の90年代を乗り切り、21世紀への飛躍を約束するWindowsパソコンには、二つのキーワードがある。「ネットワーク」と「マルチメディア」だ。
Windows 3.1の登場から一年が経過して、Windows 3.1は安定した成長を続けてきたが、今後の大きな牽引力と期待されているWindows が、Windows NTだ。
Windows NTは、最初からネットワーク環境を構築することを目的に開発されたWindowsのハイエンド版にあたる基本ソフトだ。ピアツーピア型ネットワークを実現するクライアント版と、クラアイント/サーバー環境を実現するアドバンスドサーバー版があり、企業の規模と目的に合わせて、スケーラブルなネットワーク環境の構築を支援する。
★マルチメディアを支援するVideo for Windows
もうひとつのキーワードである「マルチメディア」も、Windowsを取り巻く環境は充実してきた。
声を認識して動作するWindows Sound Systemや、音と動画を記録/再生できるVideo for Windowsの登場によって、多彩で表現力の豊かなマルチメディア情報が、目の前で利用しているWindows の画面を通して記録・再生できるようになった。また、マルチメディア技術を基盤としたユーザーインターフェースの革新は、パソコンユーザーの裾野を広げるだけではなく、パソコンによる新しい表現手段を生み出す可能性もあり、これからの成長がもっとも期待されるジャンルである。
★第三の期待
Windows によって、日本で使われるパソコンの多くが、事実上の国際化を実現したことになる。Windows ならば、海外の優れたソフトウェアや周辺装置を、すべてのアプリケーションで等しく使える道が開ける。したがって、海外の優れた製品を日本市場でも利用できる可能性が大きく広がった。
もちろん、日本語版Windows 3.1が登場してから一年以上経過した日本市場のハードウェアとソフトウェアの充実度も見逃してはいけない。当初は限られたビジネス用アプリケーションしかなかった日本のWindows 市場も、この一年で大きく成長し、ハード・ソフトともに充実してきた。それだけに、製品選びの幅も広がり、自分の目的にフィットした商品を発見する可能性も高くなっていた。
★Windows 3.1成功の理由
Windows 3.1は、発売から一年と約一ヶ月を経過して、日本の市場にも確実に受け入れられた。1994年3月に実施された大規模なシステムのアップデートサービスによって、数多くの機能アップが実現し、同時に安定したGUI環境を提供できるようになった。そして、なによりも大きな進化は、Windows対応のアプリケーションが充実してきたことにある。最新版の表計算ソフトであるExcel 5や、日本語ワープロソフトのWord 6、一太郎 for Windowsなど、数多くのビジネス用ソフトが登場し、仕事でパソコンを使おうと考えている人にとって、魅力ある環境になってきた。
どうしてWindows 3.1はこれだけの成功を収めたのか?
一般的には、初心者にも使いやすいGUI環境の提供や、アプリケーション間で統一化されたオペレーションによる教育コストの軽減などが、Windowsを導入するメリットだと言われている。しかし、Windowsが今日の成功を成し遂げた本当の理由は、もっと別のところにある。確かに、使いやすさや教育コストの軽減は、MS-DOSの時代には期待できなかったメリットだが、それだけでWindowsがこんなに成功するわけがない。
Windowsをここまで成功した最大の理由は、MS-DOSの時代の大きなボトルネックの解決にあった。
MS-DOS時代のボトルネック、それは二つの資源の欠乏にあった。
不足する資源。その一つは、メモリ資源に代表されるプログラム開発のためのリソース不足だ。MS-DOS時代に横たわっていた「最大メモリ640KBの壁」は、幾多の拡張メモリシステムを用意しても、すぐに足りなくなった。大量のメモリを複数のプログラムで共有する基本ルールもなかったため、疑似的なマルチタスク処理を実現すると、多くのトラブルに見舞われることも多かった。
この問題をWindowsは解決した。MS-DOSを基本ソフトとして起動するWindowsだが、一度システムが動き出してしまうと、そこから先は、Windows独自のメモリ管理が働いて、論理的には4GBという広大なメモリ空間をプログラムのために用意してくれる。640KBの呪縛からの解放によって、多くのソフトハウスはWindowsを歓迎した。
二つ目のボトルネックは、周辺機器を使うためのデバイスドライバの不足と混乱だった。パソコンは、その気になればあらゆるデジタル装置を繋いで使うことができる。しかし、現実の問題として、その装置を使うためには、デバイスドライバと呼ばれるシステム処理プログラムを設計しなければならない。ところが、ある装置を使うためのデバイスドライバが、応用ソフトの種類によっては、思い通りに動かないことがある。たとえば、プリンタのような身近な周辺装置も、MS-DOSの時代には、ソフトウェア毎に数多くのデバイスドライバが用意され、フロッピーディスクの多くが、これらの多様なプリンタドライバのためだけに浪費されていた。
このような状況では、たとえ革新的な周辺装置が誕生しても、デバイスドライバの不備によって、市場に受け入れてもらえないことが多々あった。この問題もWindowsが解決した。すべてのデバイスをWindowsが一元的に管理することによって、応用ソフトとデバイスドライバの依存関係がなくなり、Windowsで使えるデバイスドライバさえあれば、すべての応用ソフトからその周辺装置が使えるようになった。
この二つのボトルネックの解消によって、MS-DOSの時代には不可能だった大規模なプログラムの開発が可能になり、個々の周辺装置に依存しない優れた応用ソフトが生み出されるようになった。
その結果生まれた魅力的なソフトウェアの数々や、複雑な操作を行わないで、複数のプログラムを容易に切り替えられるウィンドウシステムなどが支持されて、Windows は今日の成功を収めたのだ。
★Windowsの持つボトルネック
二つのボトルネックの解消がソフトハウスにもたらしたメリットは、確かにWindowsを普及させる大きな原動力にはなったが、同時に新たな問題も生み出した。それは、Windows そのものの導入の複雑さだ。
もし、買ってきたパソコンに最初からWindows 3.1が導入されていて、すべて与えられたままの条件で運用する限りにおいては、Windowsの持つ複雑さに出会うことはないだろう。だがその反対に、すべてのコンポーネントを自分で構築して、Windows 3.1の導入からデバイスドライバの登録までの作業を、すべて独力でおこなおうとした時に、多くのユーザーは、Windowsの持つ複雑なメカニズムに直面し戸惑うことになる。
たとえば、ディスプレイの画面解像度は、プログラムマネージャのメイングループにある「Windowsのセットアップ」を実行して変更するが、利用するプリンタドライバの登録や変更は「コントロールパネル」の「プリンタ」で処理するとか、仮想メモリは「386エンハンスドモード」の「スワップファイルの設定」で定義する、といったややこしさだ。つまり、Windowsの基本構成を入れ替えようとし始めた瞬間から、ユーザーは、新しい専門用語と複雑な操作手順を理解しなければならなくなる。
一説によれば、Windowsが使える環境さえあれば、すべての初心者がパソコンを快適に使いこなせるような錯覚を与える情報もあるが、一般の企業で、Windowsの導入を成功させるためには、このユーザーとエンジニアをしっかりと区別して、パソコンで仕事をする人たちに、混乱が起きないようにする運用努力が必要なのだ。
★新たなボトルネックの解消を目指すWindows
もちろん、Windowsを開発したマイクロソフト社としても、そんな現状の混乱や戸惑いをそのままにしておく気持ちはない。もし、現在のままの不満を抱えたWindowsを出荷し続けていては、ユーザーが遠ざかってしまう心配もあるからだ。そのため、これから登場する予定の次世代Windows(開発コード名:Chicago)では、徹底した使いやすさの提供が、バージョンアップの大きなテーマになっている。
Chicagoにおける「使いやすさ」の向上には、ひとつのキーワードがある。「プラグ&プレイ」と呼ばれる技術だ。プラグ&プレイは、マイクロソフト社だけではなく、インテル社やコンパック社とのパートナーシップによって支援される技術で、デバイスドライバの導入を容易にするだけではなく、拡張ボードなどの周辺装置のセットアップも簡単にする。このプラグ&プレイを完全に実現するためには、Chicagoだけではなく、新しい設計機構を盛り込んだパソコンと、プラグ&プレイ規格に適合した拡張カードが必要になる。
この事実は、これからChicagoのために登場するパソコンや周辺装置が、現在の製品とは異なる進化を遂げることを意味している。もちろん、Chicagoは、既存のWindows 3.1が動作するパソコンでも利用できるようになっているが、先に説明した「導入の手間」を軽減するためのアプローチは、もうはじまっているのだ。
★もうひとつのWindowsの進化がNT
インテル社のx86ベースのCPUを対象に開発されたシステムがWindowsだとすれば、Windows NTは、CPUへの依存度を低くして、よりパワフルかつネットワーク利用を強く意識したもうひとつのWindowsになる。Windows NTとネットワークに関しては、別の紙面で紹介しているが、このWindows NTも、近くDaytonaと呼ばれるバージョン3.5が登場する。そして、このDaytonaの先には、Cairoと呼ばれるバージョンも控えている。さらに、マイクロソフト社では、このWindows NT アドバンスドサーバーを活用したビデオ・オン・デマンドシステムを構築するビデオ・サーバーとして、Tigerというシステムの構想も発表した。
使いやすさを追及するChicagoに、ネットワーク環境でのハイパフォーマンスを求めるDaytonaなど、Windowsファミリーは、これからもより幅広い需要と現状の問題解決に向けて、進化と広がりを続けていくのだ。
(著者:田中亘 wataru@yunto.co.jp)